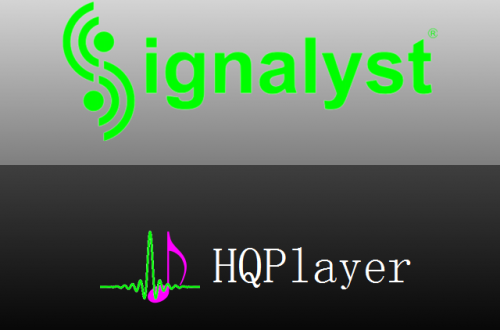HIFI日記:HIFI神話を打破し、音楽の本質へ回帰する
これはブログ主が執筆した2本目の業界日記である。最初の業界日記「デジタル配信とCDインターフェースから見る音楽業界」では、実体音楽とデジタル音楽が著作権音楽業界全体にとって持つ意義について語り、音楽媒体の発展の流れを体系的に振り返った。数年を経て、ブログ主は以下のような返信を見かけ、「HIFI」に対する自身の理解を再び語ることにした。
序論:「良い質問」から始める
新規オーディオ愛好家(新焼)であれ、ベテラン愛好家(老焼)であれ、私たちは多かれ少なかれ「私たちが追求するHIFIとは、結局のところ何を追求しているのか?」と問うたことがある。この質問は一見単純だが、現代のオーディオ消費文化の核心を突いている。ブログ主は、現在広くオーディオ愛好家(焼友)が接している「HIFI」(High Fidelity、高忠実度再生)は、その誕生の本来の目的から既に大きく逸脱していると考えている。HIFIという言葉は一般化、曲解、概念のすり替えを受け、音楽愛好家に対するトップダウン型の集団催眠、あるいは言い換えれば:PUA(精神的虐待・操作)とも言える状態を形成している。
一、 「高忠実度」という幻想:いったい誰がHIFIの定義を歪めているのか?
1. 「技術ラベル」から「身分ラベル」へ
HIFIの本来の意味は「高忠実度再生」、つまり「原音に対して高度に忠実であること」であり、これは純粋な技術概念である。しかし、商業化の波の中で、この概念は巧妙にすり替えられ、拡張されてきた。
「技術ラベル」から「身分ラベル」へ:HIFIは機器の性能を表す形容詞から、「趣味」「専門性」、さらには「階層」を象徴する名詞へと変貌した。メーカーとメディアは数十年にわたる宣伝を通じて、「音楽愛好家」と「HIFI追求者」を同一視することに成功し、「HIFIをやらなければ、本当に音楽を理解しているとは言えない」というコミュニティの雰囲気を醸成してきた。
実は、この幻想は簡単に打破できる。例えば自問してみよう:「昔の人は良い音楽を聴くに値しなかったのか?」「音楽を理解するには必ずHIFIレベルの機器が必要なのか?」答えは明らかである。このようなHIFIの定義のすり替えは、純粋な音楽鑑賞に基づくものではなく、消費主義下での身分構築である。
2. 「定義権」の争奪
なぜ「HIFI」を再定義するのか?なぜ「HIFI」という言葉を選ぶのか?まず、HIFIという言葉は抽象的な概念であり、一連あるいは複数のオーディオ関連技術や追求を統一して概括したものである。英語でも翻訳された中国語でも、非常にシンプルで分かりやすい。メディアも個人もこの言葉を容易に使用できる。現代流行りの「AI」「メタバース」といった言葉と同様の概念である。
しかし問題は、HIFIという言葉自体の概括性と抽象性にある。長い時を経て、HIFIは「高忠実度」という核心を保ちつつも、その「範囲」や「細部」は繰り返し再定義されてきた。そして、この唯一無二の「定義権」を巡る争奪戦こそが、現在の「HIFI」が極端に一般化され、曲解され、PUAの道具として広く利用されるようになった元凶である。
HIFIメーカーにとって、宣伝・プロモーションのニーズを満たしつつ、技術的詳細の等級分けも可能にする標準は特に重要である。実際、HIFI分野にはこの種の「標準」が不足しているわけではない。技術志向の「ハーマンカーブ」、主観志向の「オーディオ二十要」は、本質的にオーディオ分野に奉仕する標準である。実際、共通の標準があることは確かに良いことであり、そうでなければマーケティング勝負になってしまう。
したがって、研究開発能力の強いメーカーは、その開発力と資本力を利用して、HIFIをSN比、歪み率、周波数特性曲線などの定量化可能な技術指標として定義し始めている。パラメータが高ければ高いほど「HIFI」であり、価格も高くなる。この時点で、HIFIはメーカーが合理的なプレミアム価格を設定するための「科学的」根拠となり、多くの友人が以前からこの問題に気づいており、これと区別するために「科HI」(科学HIFI、スペック重視のHIFI)という呼称を生み出している。よく考えてみると、「科HI」は明らかに揶揄的なニュアンスを持つ新語であり、本質的には、オーディオ愛好家が「パラメータ・指標」が「HIFI」の定義権を侵していることに対する合理的な抵抗である。
ただし、ブログ主は「パラメータと指標」を用いてハードウェア機器を論じることには反対どころか賛成であることを明言する。しかし、3C認証(中国の強制製品認証)を通ったモバイルバッテリーでも爆発しないとは限らないように、「パラメータと指標」はあくまで製品の最低限の基準を測るものであり、最も核心的な使用体験、リスニング体験はリスナーが決めるべきである。しかし、この問題は、次に重点的に議論すべき「定義権争奪」の焦点であるKOL(キーオピニオンリーダー)に繋がる。
伝統的なHIFIブランドに対して、新規ブランドが参入する最良の方法は何か?見栄えの良い製品を作り出すことか?製品の音の可能性を引き出すことか?実はどちらでもない。現在の新興HIFIブランドの大多数が選択する方法は:KOLを創造することである。彼らは通常、ブランドの個性を作り出し、キーとなるチューニング担当者、あるいは社長自身の「独特のセンス」や「業界経験」を提示し、ブランドに結びついた「独特のチューニング」を強調する。この行為は、一見すると「HIFI」が芸術的追求を表現する行為であることに従っているように見える。しかし、皆さんがよく考えてみると、ブランドの意見リーダーを形成するこのような方法は、実際にはリスナーの発言権を剥奪または低下させる行為であることに気づくだろう。KOLたちはHIFIを定量化が困難な「芸術的感覚」と定義し、コミュニティマーケティングを通じてブランドロイヤルティを形成し、自社製品を「本当に音楽を理解している者の選択」と定義する。
このような手法は古くから存在し、今日では業界のルール(あるいは暗黙の了解)の一部となっている。ただし、多くの高価な趣味に比べて、HIFIは集団的規律付け(グループ・コントロール)という点で確かに一層深く、遠くまで進んでいる。定量化されたパラメータによる定義であれ「KOL」による定義であれ、この二つの道筋の最終目的は同じである:自社製品に権威を与え、商業的価値を実現すること。そして消費者側から見れば、私たちは常に情報の繭(フィルターバブル)の中に閉じ込められ、知る権利と発言する権利を徐々に奪われていく。よく思い返してみてほしい、あなたはもうとっくに、どのメーカーの提供する文案(プロモーション文)からも製品の本当の実力を知ることができなくなっていないだろうか?
二、音楽は芸術であり、科学実験ではない
抽象的な芸術としての音楽の魅力は、その不確実性と多義性にある。作曲家、演奏家、レコーディングエンジニアが共同で一次創作を完成させるが、それは芸術連鎖の前半に過ぎない。リスナーの耳と脳が介入する時、二次創作が真に始まる。リスナーの個人的経験、感情状態、文化的背景、さらにはその時の環境さえもが、音楽そのものと化学反応を起こし、唯一無二の感覚を生み出す。
同じく芸術である「絵画」「文学」などの分野では、「千人の読者には千人のハムレットがいる」とは聞くが、「作者の意図通りにハムレットを理解しなければならない」という論調はほとんど聞かない。同様に、「モナリザの微笑」の秘密を本当に解き明かすことは不可能である。なぜなら、解明しようとする行為そのものが、芸術表現に対する裏切りだからである。
したがって、(創作であれ鑑賞であれ)音楽を一つの要求、一つの目標で規律付けようと強いるならば、芸術は創造の土壌を失い、音楽もまた消滅するだろう。実際、「ラウドネス戦争」がもたらした悪果は、現在の音楽業界が直面する重要な課題であり、これもまた集団的規律付けによって生じた結果である。
ブログ主の専門分野から言えば、心理音響学(Psychoacoustics)の研究は、とっくに根本的な事実を明らかにしている:私たちの聴覚は高忠実度レコーダーではなく、創造性に満ちた脳のデコードシステムである。物理的な音波と私たちが知覚する音の間には、巨大な溝が存在する。簡単な例を挙げよう:MP3の聴覚マスキング効果(Auditory Masking)。技術的には、MP3は非可逆圧縮フォーマットである。ファイルサイズを縮小するために、元のオーディオファイルから大量のデータを永久に、不可逆的に削除している。機器で測定すれば、MP3の波形と元のCD音源の波形には大きな差があり、絶対的に「忠実ではない」。なぜ私たちの大多数が高ビットレートMP3とロスレス音楽の違いを聞き分けられないのか?それは、心理音響学の「聴覚マスキング効果」を巧みに利用しているからだ——強い音はその近くの周波数の弱い音を「マスク」し、人間の耳がその弱い音を感知できないようにする。MP3の原理は、まさにこの「どうせ聞こえない」音声情報を削除することにある。
この例を挙げたのは、一つの論点を説明するためである:人間の脳は音を単にそのまま受け入れるのではない。MP3の非可逆性は「ロスレス」と認識され、レコードの「欠陥」は人間の脳の知覚において美的な「味わい」へと変換される。したがって、誰かが特定の音を「HIFIではない」と批判する時、彼らはおそらく見落としている。究極の「HIFI」追求は、本質的に音楽の基盤に背いているのだと。音楽の魅力のすべては、まさにそれが物理法則を巧妙に利用して、私たちの主観的な知覚の琴線に触れる点にある。そして人類の複雑で壮大な音楽史は、客観的な指標の冷たい基盤の上ではなく、この主観的な体験という肥沃な土壌の上に築かれている。人間の脳による音の二次加工こそが、複雑で壮大な音楽の歴史に対する最良の注釈なのである。
三、 録音スタジオから始まる長い道のり
それでは、音楽と共に、その誕生からあなたの耳に届くまでの旅を一緒に辿ろう。この過程の中で、HIFIは一体どこに位置するのか?リスナーにどんな啓示をもたらすのかを考え、理解してみよう。
1. 音源と環境 (The Source & The Room):
音の出発点として、ヴァイオリンを例に挙げる。ヴァイオリンに詳しい友人はよく知っているが、ヴァイオリンは安いもので数百円、高いもので数百万円もする。異なる素材、異なる年代、異なる職人、異なる演奏者、異なる弓使いによって、ヴァイオリンから音が発せられたその瞬間から、音は既に千変万化である。レコーディングエンジニアはマイクを持ち、理想的な録音スタジオを見つけ、部屋の音響特性(残響、定在波など)を測定し、録音角度と距離を測定した後、初めて録音ボタンを押す。
HIFIにとって、この音源のコントロール可能性は「極めて悪い」と言える。これは録音の質が悪いという意味ではなく、このプロセス全体がリスナーにとっては完全なブラックボックスであり、リスナーが録音源の状況を知る方法はほとんどないということだ。制作完了後に録音環境と機器を公開するアルバムはごく少数である。厳密に言えば、音楽が録音された元の状態を知ることができなければ、「高忠実度」の「真」はどこに行くのだろうか?
2. 収音 (Microphone & Placement):
これは「レコーディングエンジニア」が道具を選ぶ最初のステップである。どのタイプのマイク(ダイナミック、コンデンサー、リボン)を使用するか?楽器からどれだけ離れた場所、どの角度に置くか?これらの選択は音色、ダイナミクス、空間感に大きく影響する。これはすでに単純な信号収集ではなく、芸術的な決断である。業界内ではほとんどの録音に「慣例」があるが、実際にこのステップで現れる効果は天と地ほどの差がある。最初のステップと同様に、このステップの内容も高度なブラックボックス状態にあり、ほとんど検証不可能である。
3. 録音とミキシング (Tracking & Mixing):
現代音楽は通常、マルチトラック録音である。ミキシングエンジニアはオーケストラの指揮者のように、多くの内容について決断と調整を行う。
| レベルとパンニング (Levels & Panning) | 各楽器の音量とステレオ空間内の位置を決定する。 |
| イコライゼーション (EQ) | 異なる楽器の周波数帯域をブーストまたはカットし、よりクリアに、あるいはより特徴的にする。 |
| ダイナミクス処理 (Dynamics) | コンプレッサー、リミッターを使用して音量の変動を制御し、音をより力強く、あるいはより滑らかにする。 |
| 空間効果 (Effects) | リバーブ、ディレイなどのエフェクトを加え、特定の空間感や雰囲気を作り出す。 |
ついにミキシングのステップに到達し、ようやく多くのオーディオ愛好家が口にする「レコーディングエンジニアがあなたに聴かせたい内容」の場所にたどり着いた。しかし残念なことに、元の録音はミキシングを経て、いわゆる「元の信号」は最早存在しない。私たちが聴いているのは、実際にはミキシングエンジニアがその専門的判断と芸術的審美眼に基づいて再構築した音楽シーンである。そして現代の録音では、電子シンセサイザーやエフェクターが続々と登場し、クラシック音楽を除けば、電子シンセの痕跡が全くない音楽はほとんど見られない。いずれにせよ、音楽はこの段階でほぼ形が決まり、HIFI愛好家はようやく追求できる源を見つけ、「高忠実度」の「真」とはこのステップを指すのだと理屈に合うように言える… だろうか?
4. マスタリング (Mastering):
これはオーディオ制作の最終工程であり、マスタリングエンジニアが担当する。彼は「品質管理ディレクター」のように、以下のことを担当する:
| 統一性 | アルバム内の全ての曲のラウドネスと音色のスタイルを調和させ、統一させる。 |
| 最適化 | ストリーミング、CD、レコードなど、異なる配信媒体に対して最終的なEQ、コンプレッション、ラウドネスの最適化を行う。例えば、ストリーミングプラットフォーム向けには、プラットフォームによる圧縮を避けるため、特定の基準(例:-14 LUFS)内にラウドネスを制御する必要がある。 |
| エラー修正 | 録音中に存在する可能性のあるエラーを手作業で修正する。 |
かつて、マスタリングは一般的にレコード盤の原盤制作を指していたが、現代のマスタリングは通常、ミキシングが完了したオーディオリソースファイルを指す。しかし、マスターの配布は単に各ストリーミングプラットフォームに渡せば終わりというわけではない。現在、世界中のほぼ全てのストリーミングサービスは、アップロードされたオーディオに対して何らかの制限を避けられず、プラットフォームに応じて異なる提示戦略が取られるからである。先に述べたラウドネス戦争は、ここで白熱の段階を迎える。
私たちが聴く最終的な完成品は、演奏者、レコーディングエンジニア、ミキシングエンジニア、マスタリングエンジニアによる層状の「再創作」の結果である。HIFI機器が追求できる「忠実度」は、せいぜい「録音とミキシング」というステップ後の「調理済みの料理」を忠実に再現することまでであり、「録音現場」という「源」からは程遠い。そしてこの源は、音楽の演奏者でもなければ、必ずしも録音したミキシングエンジニアでもなく、より大きな可能性としては、各ストリーミング、配信プラットフォームの戦略に由来するものである。したがって、オーディオの「オリジナル版」を盲目的に神聖視し、マスターレベルの再現を無思考に追求することは、確かに大きな誤解である。
四、技術指標の真の意義
ブログ主は決してHIFI機器の価値を否定しているわけではない。何しろ本人の所有機器は既に6桁(数十万円)に達しており、大多数の「オカルト」(主観的要素)にも肯定的な態度を示している。ブログ主はまた、ほとんどのHIFI指標が、価格設定戦略や基礎的な性能の参考としての意義を認めている。疑いなく、それらは音楽表現を実現する基盤と保証である。劣悪な再生システムは、その深刻な歪み、狭い周波数特性、弱々しいダイナミクスレンジによって、音楽の中に本来感知されるべきディテールと感情を、ぼやけたすりガラスのように覆い隠してしまう。
| 解像度 (Resolution) | 歌手の息継ぎのディテール、弦が擦れる質感などを聴かせてくれる。これらは感情を構成する微細な要素である。 |
| ダイナミックレンジ (Dynamic Range) | 音楽をささやくような音量から雷鳴のような轟音まで届けることを可能にし、強い感情の対比を伝える。 |
| 過渡特性 (Transient Response) | ドラムビートの衝撃力とリズムの正確さを決定する。これは音楽の骨格である。 |
| 音色の正確性 (Timbre Accuracy) | 異なる楽器の独特な音色を識別し、それらが伝える感情の色彩を感じ取ることを可能にする。 |
关键在于,这些技术指标是服务于“感受音乐内容”这个最终目的的工具。它们构建了一个足够清晰、稳定的平台,让音乐的情感得以顺畅地流淌。当技术指标达到某个“足够好”的水平后,再往上的提升所带来的边际效益会急剧递减,而个人审美的差异性则会凸显出来。而至于蔡琴老师到底有几分悲、几分伤,这琴声到底几分潮,几分干这种离谱到姥姥家的HIFI评判标准,则完全不符合现实,也凸显出部分魔怔HIFI群体的病态特征。
肝心なのは、これらの技術指標は「音楽の内容を感じ取る」という最終目的に奉仕する道具であるということだ。それらは十分にクリアで安定したプラットフォームを構築し、音楽の感情がスムーズに流れ出ることを可能にする。技術指標がある「十分に良い」レベルに達した後は、それ以上の向上がもたらす限界効用は急激に減少し、個人の審美観の差異が顕著になる。そして、蔡琴(ツァイ・チン)先生の歌声に悲しみが何割、哀しみが何割含まれているかとか、このヴァイオリンの音が何割湿っていて、何割乾いているかというような、とんでもなく現実離れしたHIFI評価基準は、完全に現実にそぐわず、一部の病的なHIFI集団の病的な特徴を浮き彫りにする。
五、 自律した音楽リスナーになるには
ここまで真剣に読んでくれたなら、ブログ主が伝えたいことを理解してくれたかもしれない。まず第一に、HIFIという言葉は業界全体によって曲解され、ユーザーを縛る道具として使用され、事実上「金を払ってHIFIでないものを買う=バカ」あるいは「HIFIでない=音楽を理解していない」という病的な状態を形成している。「聴き心地の良さを追求する」ことは大多数の「HIFI人」に軽蔑され、蔑視の連鎖の最底辺に位置している。このような状況下で、この風潮を逆転させることは最早絶望的だが、これらの「業界基準」に勇敢に向き合い、自らの感じ方やニーズを率直に語ることは、音楽を好きな友人が誰でも行うべきことである。そのために、ブログ主は参考までにいくつかの見解を提示する:
- 自分の耳を信じ、個人の基準を確立する: レビューやパラメータは参考にできるが、最終的な審判はあなた自身である。様々なものを聴き、比較し、あなたを没入させ、機器の存在を忘れさせるような音を見つけ出そう。
- ニーズを明確にし、盲従しない: 主にどんなジャンルの音楽を聴くのか?あなたのリスニング環境はどんなものか?予算はどれくらいか?クラシックに適したシステムがロックに適しているとは限らない。最高のものはなく、最も適したものだけがある。
- 「集団催眠」に警戒する: あるブランドや製品がコミュニティで「神」として崇められる時、冷静さを保とう。その背後には往々にして商業的な動きがある。独立して考え、他人の選択を尊重しつつ、自分の判断を貫こう。
- HIFIを終着点ではなく旅と捉える: 異なる機器、異なるチューニングスタイルを探求する過程そのものが楽しみに満ちている。それはあなたの美的境界を広げ、より多くの次元から音楽を理解させてくれる。しかし、この過程を終わりのない「機器への不安」に変えてはならない。
- 最終的に、音楽へ回帰する: 新しい音楽を探求したり、好きな作品を深く理解したりすることにより多くの時間を費やそう。機器は舟であり、音楽は海である。私たちの目的は航海することであり、この舟を際限なく磨き、崇拝することではない。
六、結語
HIFIは偉大な技術的ツールであり、私たちがこれまでになく高品質な音楽に近づく可能性を提供してくれた。しかし、私たちははっきりと認識しなければならない:ツールはあくまでツールであり、決してツールを崇拝してはならない。真の音楽体験は、私たちと芸術との間にある、唯一無二で複製不可能な感情的な共鳴から生まれる。唯一の「絶対的な基準」への執着を手放し、多様な審美観を受け入れ、最終的に自らの心の奥底へと通じる「高忠実度」への道を見つけよう。